持続可能な⾷の未来へ
⽇本の料理⼈・シェフのサステナビリティ・マニフェスト
2030年へ向けた17の指針
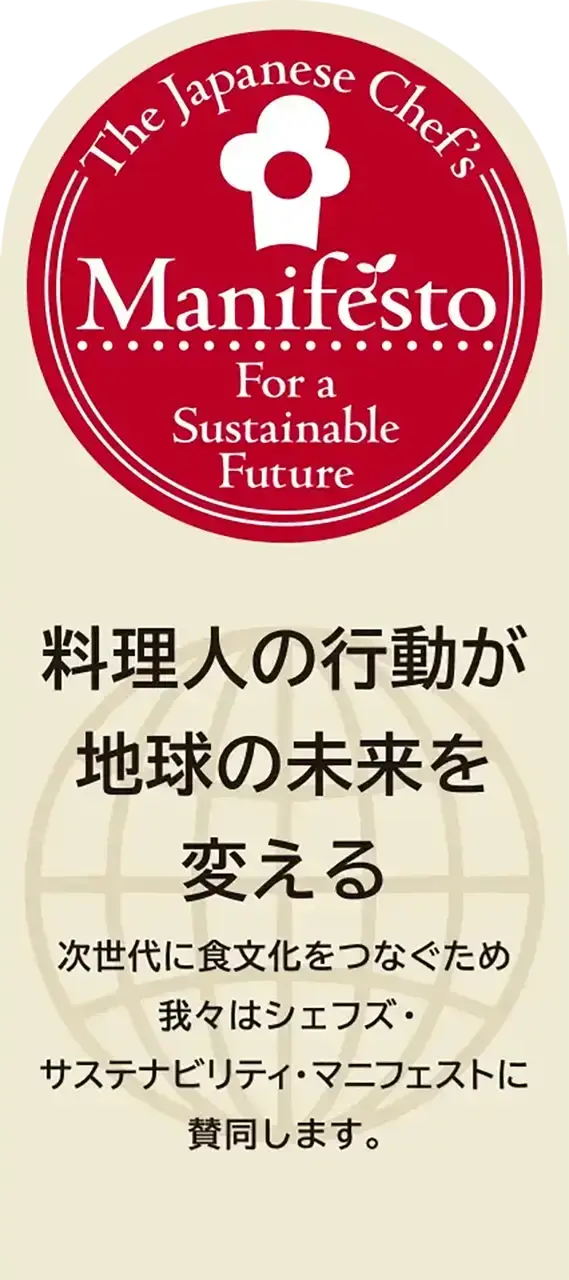

⾷⽂化の継承と多様性
⽇本の⾷⽂化や伝統料理を理解し表現する。
⽇本の豊かな⾃然からの恵みである⾷材に感謝し⾃然を敬う精神を⼤切にする。また⽇本各地に受け継がれてきた多様な⾷⽂化や、発酵⾷品をはじめとする⾷の伝統、知恵、⼯夫、慣習を表現する。そして、⾷事は命をいただく⾏為であることを深く理解し、その感謝の気持ちを料理に込めて伝える。
世界の伝統料理との融合を模索する。
⽇本各地の伝統料理を継承し尊重するとともに、世界の伝統料理にも同等の敬意を払い、サステナビリティを基本に据えながら、それぞれの料理と⽂化が共存し調和する新たな⾷⽂化の可能性を模索する。
料理を通じて会話と笑顔を⽣み出し、⼈々の⼼を結びつける。
⾷事は、栄養補給ではなく、⼈と⼈をつなぐ特別な時間でもあり、⽇常的な時間でもある。料理⼈として、⾷を通じて⼈々の⼼を結び、家族や友⼈が共に過ごす⼤切なひとときを創り出すことも使命の⼀つである。料理を提供することは、おいしさを届けるだけでなく、会話と笑顔を⽣み出し⼈々の絆を深める役割を果たす。料理⼀品⼀品に想いを込め、⼼温まる時間を演出する。
調達
生産者を支援し、地元産と旬の食材を使用する。
日本が育んできた「自然と共生し調和を重んじる」という自然観を基礎に、日本各地の里・山・海が持つ気候や風土、地形、水域を活かした地元産の食材を積極的に使用し、地域の食文化の継承を行うとともに原風景を守り、地域に活力を与える機会とする。また、四季を意識し、自然のリズムに寄り添った旬の食材を料理に取り入れる。また生産者の高齢化が進む現状を踏まえ、食料自給率を維持・向上させるため、地域の生産者を支援するとともに、自産自消の取り組みも推進する。
健康な土壌で生産された農産物を使用する。
自然との調和を尊重し、健康な土壌と生物多様性が保たれた環境で生産された農産物(例:無農薬や無化学肥料の作物)を使用する。自然が育んだ素材の持ち味を最大限に引き出し、食べる人が本来の味覚に目覚める一皿を届け、真のおいしさを追求する。
絶滅危惧種や数が減少傾向にある魚の使用を避け、
追跡が可能な水産物を使用する。
絶滅危惧種や数が減少傾向にある魚、またその稚魚や魚卵の使用は避ける。漁師や水産業関係者と連携し、環境影響の少ない漁法で獲れた天然魚や、環境に配慮した餌や汚染のない状態で育てられた養殖魚、認証魚を含めて追跡が可能な水産物を使用する。IUU(違法・無報告・無規制)漁業由来の魚は排除し、水産資源の有効活用として未利用・低利用魚の活用も進める。
アニマルウェルフェアと環境に配慮した畜産物を使用する
アニマルウェルフェア(動物福祉)1を重視し、平飼いや放牧など倫理的な飼育方法で育てられた畜産物を選ぶ。自然環境や社会に配慮した飼料を使用して育てられた食肉を提供する。さらに農作物被害対策として捕獲された野生鳥獣(猪や鹿など)をジビエとして活用し、地域資源としての価値を高め、食文化の多様性に貢献する。
植物性食品を積極的に取り入れる。
植物性食品2の提供を増やし、野菜・果物・豆類・全粒穀物を中心に据えたメニューを取り入れることで、伝統的な食文化を尊重しつつ、バランスの取れた植物性食品の料理を提案する。また、肉や乳製品を使用しない日を設定するなど、動物性食品の使用を控えめにし、代替タンパク質として豆類、ナッツ、発酵食品などを活用し、栄養価を損なわずに提供する。
食のサプライチェーンに関わる全ての人権を尊重し、
環境にも配慮した調達を行う。
国内外を問わず、サプライチェーン上の生産・加工・流通に関わるすべての人々の人権を尊重し、自然環境にも配慮した調達を行う。また、エシカル認証品を優先的に使用し、公正な価格設定や適切な労働環境の提供、児童労働や強制労働の排除を徹底する。また、サプライチェーン上の人権や環境に関するリスクを特定する行動3を計画的に実施するとともに、持続可能な森林管理やコミュニティ支援への配慮を行う。
環境
エネルギーの使用を減らし、カーボンフットプリントを削減する。
地元産で旬の食材の使用することに加え、省エネルギー技術や環境負荷を低減する最新の調理技術や機材を選択し、キッチンでの資源使用量と環境影響を削減する。また店舗のカーボンフットプリント4を計算するとともに、環境影響が高い食材とは何かを理解し、レシピの環境影響の情報を提示する。さらに再生可能エネルギーの使用や省エネルギー施策の実行、環境影響を減らす食材選択に取り組む。
食品ロスを削減し、食材を無駄なく活用する。
食品ロス削減は、料理の質向上と経済効率化の両面で重要な取り組みである。適量での提供、食材の最適利用、在庫管理の徹底、地元産食材の使用による輸送ロス削減、料理の残りの持ち帰りの推奨や寄付などを実施する。また、廃棄される食品は焼却せず、持続可能な廃棄物処理(飼料・肥料・燃料等へのリサイクル)を目指す。
資源の使用を削減し、再利用やリサイクルを通じて
無駄をなくす。
缶・ビン・PETボトル、紙、段ボール、紙パックなどを資源として扱い、①リデュース(削減)、②リユース(再利用)、③リサイクルの優先順位で取り組む。使い捨てプラスチックの削減を推進し、再利用可能な包装材や生分解性素材を活用して廃棄物の発生を最小限に抑える。また、効率的な資源利用を図り、使用済み製品の再利用やアップサイクル、リサイクルを促進することで、サーキュラーエコノミー5の実現を目指す。
生産者と連携して生物多様性の保全と
自然環境の回復に貢献する。
持続可能な農産物、水産物、畜産物の使用を進め、それらを生産する一次産業関係者と積極的にコミュニケーションを図る。生物多様性保全に向けた協働を検討し、具体的な行動を実践することで、自然環境の保護と回復を目指し、ネイチャーポジティブ(自然再興)6の実現に貢献する。
社会
誰もが公平に評価され、安心して働ける職場環境をつくる。
飲食店の労働者が公平に評価され、適切な処遇を受けられるよう、業績評価・スキル開発・キャリア形成を重視する。公正な報酬や福利厚生の提供、労働環境の改善に努め、多様性と包摂性を尊重する。また、適正な昇進制度や労働時間の管理を徹底し、労使関係の強化にも取り組む。そして、誰もが尊重され、差別や偏見なく、安心して働ける職場環境を整える。
健康と地球環境に配慮した食事を提供する。
食品の安全性と健康への影響を考慮し、添加物(合成保存料、人工甘味料、合成着色料、人工香料、酸化防止剤、発色剤、乳化剤、加工助剤など)について、科学的な知見をもとに厳選して使用し、安全で健康的な食事を提供する。また、健康と地球環境に配慮7し、植物性食品を中心とした持続可能な食材の活用を推進する。さらに、新しいバイオテクノロジー技術8に関係する食材については、その情報をメニュー等に明示し、消費者が選択できる仕組みを整え、食の透明性を高めることで、より健康的で持続可能な食文化の形成に貢献する。
栄養バランスの取れた食事を提供する。
栄養バランスの優れた食事は、身体を健やかに保つだけでなく、心の安定や感情の豊かさにもつながる。食事は心身の健康も支える重要な要素であることを認識する。また発酵食品など、腸内環境を整える効果があるものや栄養価の高い食事を提供する。
リーダーシップを発揮し、パートナーシップを締結して、
サステナビリティの意識啓発を行う。
一次産業関係者や食品企業、流通業者、大学、行政機関などと連携し、サステナビリティの重要性を広める活動を推進する。また、地域コミュニティとも協力し、持続可能な取り組みを支援しながら、地域社会全体での意識向上を目指す。これにより、気候変動や生物多様性への悪影響を最小限に抑え、持続可能なフードシステムの構築を目指す。
脚注
- アニマルウェルフェア(動物福祉):動物が生きて死ぬ状態に関連した、動物の身体的及び心的状態で、家畜を快適な環境下で飼養することにより、家畜のストレスや疾病を減らすことが重要で、結果として、生産性の向上や安全な畜産物の生産にもつながるもの。アニマルウェルフェアでは、次の「5つの自由」を確保する。①飢えと渇きからの自由、②不快からの自由、③痛み・傷害・病気からの自由、④恐怖や抑圧からの自由、 ⑤正常な行動を表現する自由。
- 植物性食品:植物由来の食品を重視し、動物性食品の消費を減らすか排除する多様な食習慣を構成する。
- 人権・環境デュー・ディリジェンス:企業が事業活動やサプライチェーンにおいて人権侵害や環境への悪影響を防ぐために、リスクの特定、予防策の導入、監視と評価、報告と透明性の確保を行うプロセス。
- カーボンフットプリント:製品やサービスの原材料調達から廃棄、リサイクルに至るまでのライフサイクル全体を通して排出される GHG の排出量を CO2 排出量に換算し、製品に表示された数値もしくはそれを表示する仕組み。
- サーキュラーエコノミー:従来の3Rの取組に加え、資源投入量・消費量を抑えつつ、ストックを有効活用しながら、サービス化等を通じて付加価値を生み出す経済活動であり、資源・製品の価値の最大化、資源消費の最小化、廃棄物の発生抑止等を目指すもの。
- ネイチャーポジティブ(自然再興):自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させること。
- プラネタリーヘルス、プラネタリーヘルスダイエット:「⼈と地球は別々な存在ではなく、相互依存関係にある」という考えを基盤に、多様な⽣物が⽣かし合う⽣態系を維持し、⼈を含めた地球全体の健康を実現することをプラネタリーヘルスと呼ぶ。またその健康を維持しながら地球環境への負荷を減らすことを⽬的とした⾷事法のことをプラネタリーヘルスダイエットと呼び、植物性⾷品を中⼼にしつつ動物性⾷品を控えめにすることで、持続可能な⾷⽣活を実現する考え⽅。
- 新しいバイオテクノロジー食品:遺伝子組み換え技術、ゲノム編集技術、さまざまな育種技術(重イオンビーム放射線育種等)によって生産された食品。
参考文献
- 農林水産省(2023)『アニマルウェルフェアについて』
取得元:https://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/animal_welfare.html(アクセス日:2025年1月31日) - Farm Animal Welfare Council(FAWC)(1979)『ファイブ・フリーダム(Five Freedoms)』
取得元:https://webarchive.nationalarchives.gov.uk (アクセス日:2025年1月31日) - 世界保健機関(WHO). (2021). 『Plant-based diets and their impact on health, sustainability and the environment』. 世界保健機関ヨーロッパ地域事務局.
https://apps.who.int/iris/handle/10665/349086(アクセス日:2025年1月31日) - 経済産業省(2022)『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』経済産業省
取得元:https://www.meti.go.jp/press/2022/09/20220913003/20220913003-a.pdf (アクセス日:2025年1月31日) - 環境省(2020)『バリューチェーンにおける環境デュー・ディリジェンス入門』環境省
取得元:https://www.env.go.jp/content/900497033.pdf (アクセス日:2025年1月31日) - 経済産業省・環境省(2023)『カーボンフットプリント ガイドライン』経済産業省・環境省
取得元:https://www.env.go.jp/content/000124385.pdf(アクセス日:2025年1月31日) - 環境省(2023)『環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書 第2節 循環経済への移行 1 循環経済(サーキュラーエコノミー)に向けて』環境省
取得元:https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/r03/html/hj21010202.html (アクセス日:2025年1月31日) - 環境省(2023)『環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書 第2節 自然再興(ネイチャーポジティブ)』環境省
取得元:https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/r06/html/hj24010202.html (アクセス日:2025年1月31日) - イート・ランセット委員会(2019)『持続可能なフードシステムからの健康的な食事―食事と地球と健康』EAT-Lancet Commission
取得元:https://eatforum.org/content/uploads/2024/02/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report_Japanese.pdf(アクセス日:2025年1月31日) - 欧州議会 Greens/EFA 編(2021)『Gene Editing Myths and Reality - A Guide Through the Smokescreen』欧州議会. 参照URL(原文):
https://extranet.greens-efa.eu/public/media/file/9065/6768(アクセス日:2025年1月31日)
参照URL(和訳): https://v3.okseed.jp/wp-content/uploads/2024/07/okseed_GMguidebook_n3_220327_FIX.pdf(アクセス日:2025年1月31日) - 文部省、厚生省、農林水産省(2016)『食生活指針』文部省、厚生省、農林水産省
取得元:https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/shishinn.html(アクセス日:2025年1月31日)
Take Action
共に、持続可能な⾷の未来を創りましょう
私たちは、このマニフェストに込めた想いを、より多くの料理⼈・関係者の⽅々と共有したいと考えています。
このマニフェストに共感された⽅は、ぜひSNS 等でのシェアや、ご⾃⾝のサステナビリティの実践例を発信してください。
今後、賛同いただいた皆様とのネットワークをさらに強化していきます。
私たちの⼿で、「おいしさ」と「サステナビリティ」が両⽴する豊かな⾷⽂化を、⼀緒に育てていきましょう!
シェフズ・サステナビリティ・マニフェストにご賛同いただくメリット
賛同いただくことで、以下についてご提供させていただきます。
- 賛同者⼀覧でのご紹介ウェブサイト上で貴店・貴社名をご紹介します。
- 最新情報の共有サステナビリティに関する最新のイニシアティブやキャンペーン情報をお届けします。
- 知識・ノウハウの共有持続可能な取り組みに関する情報や事例を共有します。
- ネットワークの構築イベントやワークショップへの参加機会を提供し、志を同じくする仲間と繋がることができます。
-
 賛同バナーの利⽤ウェブサイトや店舗でご利⽤いただける「賛同」を⽰すバナーデータをご提供いたします。
賛同バナーの利⽤ウェブサイトや店舗でご利⽤いただける「賛同」を⽰すバナーデータをご提供いたします。

